今年、2020年の春から日本でもいよいよ5Gの商用サービスが開始されます。
ニュースや雑誌等でも『5G』と言う言葉を目にする機会が増えてきました。
ですが、『5G』っていったい何なのかを正確に理解している人はそんなに多くなくて、
なんとなくスマホの通信回線のことで『3G』、『4G』と来たから次は『5G』なんじゃない?くらいのイメージの人がほとんどだと思います。
4Gの回線でスマホを使って充分快適に動画が見られるしSNSやるにも何するにも不便はないし満足してるのに、それよりすごい5Gなんて始まっちゃったら一体どうなるの?
これ以上何がどう進化するの?ということで、5Gについて調べてみました。
5GのGってどういう意味?

5GのGはGeneration(世代)の略です。
5th Generation(第5世代)を略して5Gと呼びます。
現在日本国内で主に利用されている通信サービスは4Gで、これは第4世代の通信サービスと言う意味です。
みなさんのスマホの画面の上の方にも『4G』と表示されていると思います。
5Gについて知る前に、第1世代~第4世代までの通信サービスがどのように進化してきたのか、簡単にまとめてみます。
1G・・・1980年代に開始されたアナログ方式の最初の携帯電話サービスです。
2G・・・1990年代に開始されたデジタル方式のサービス。デジタル化によって通話だけでなく、メールをはじめ、iモード、EZweb等のデータ通信サービスを携帯電話で利用できるようになりました。
3G・・・2001年に開始されたサービス。初めて国際標準として定められ、これによって日本の携帯電話端末を海外でも使えるようになりました。NTTドコモの『FOMA』は世界で初めて3Gの商用サービスとして開始された。この頃、2008年にソフトバンクから『iPhone 3G』が発売されました。
4G・・・2012年から開始され、現在主流になっているサービスです。スマートフォンの機能をフルに活かせるように通信速度が速くなり、動画やゲームのような大容量コンテンツを快適に利用することができるようになりました。
と、1G~4Gまではこんな感じで進化してきました。
それでは、4Gの次の世代の5Gと言うのはいったいどういうものなのでしょう?
5Gの特徴
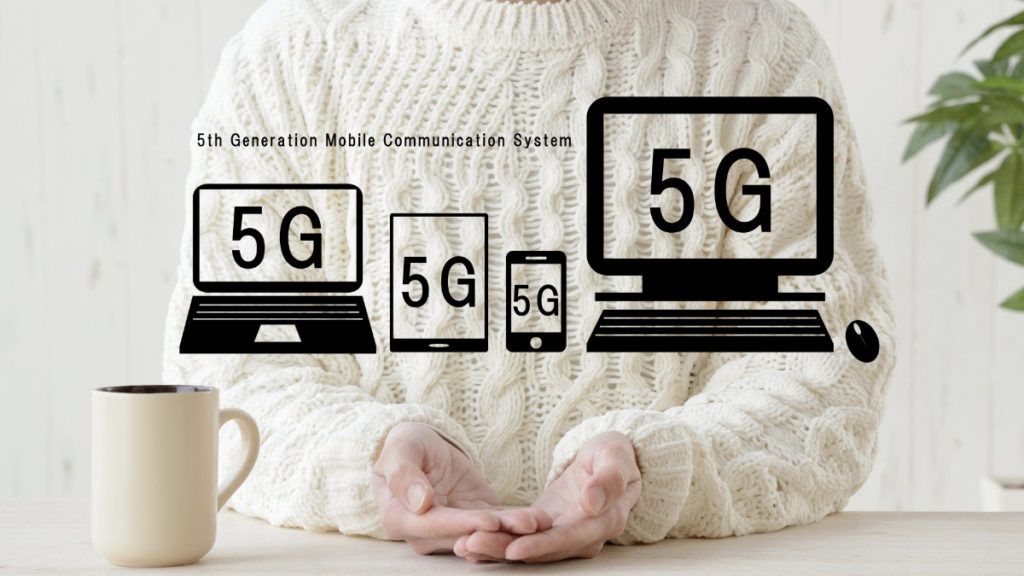
まずは5Gのキーワードとも言える特徴を3つ挙げます。
●超高速
●低遅延
●多数同時接続
この3つのキーワードが5Gの特徴をよく表しています。
それではそれぞれのキーワードについて説明します。
超高速
5Gでは下り20Gbps、上り10Gbpsの超高速のデータ通信が可能になります。
20Gbpsと言われてもどれくらい速いかイメージし辛いと思いますが、これは現在スマホで利用している4G/LTEの100倍以上の速度で、光回線よりも高速です。
大容量のデータを瞬時にやりとりすることが可能になります。
低遅延
4G/LTEの10分の1となる、1ミリ秒以下の低遅延を実現します。
低遅延と言う言葉からはスマホで動画を視聴する際の読み込み時間が短くなるようなイメージをしがちですがそういう意味ではありません。
5Gの低遅延はあくまで無線区間の遅延を短縮すると言うもので、これによってほぼ遅延なくリアルタイムで遠隔地にある機械やロボットを制御することができるようになります。
多数同時接続
4G/LTEの100倍となる1k㎡あたり100万台の端末を同時接続出来ます。
1k㎡辺り100万台と言ってもピンと来ないかも知れませんが、これはすごい数で、例えば世界中の全ての人間がスマホをネットに同時接続してもここまでの同時接続数には届きません。
ではなぜここまで多数同時接続が出来るようになっているかというと、今後スマホやPCだけではなく、様々なIOT機器が多数同時にネットに接続される状態を想定しているからです。
現在、テレビやスピーカー等、様々な家電がネットに接続されつつありますが、今後更にこの流れは加速します。
私たちの身の回りの機器全てが常にネット接続されている状態になっても耐えられるよう、5Gはこのような設計になっています。
このように、“速くて、大人数が同時に接続出来て、接続している全ての機器が遅延なくデータを受け取ることができる” というのが5Gです。
5Gで何ができるの?

それでは、“超高速”、“低遅延”、“多数同時接続”の5Gで一体何ができるのでしょう?
5Gが普及すると私たちの生活はどう変わるでしょうか?
ライブやスポーツ観戦で新しい視聴体験
5Gの高速大容量通信によって複数アングルの高画質動画を同時に配信し、見る側が瞬時に好きな映像に切り替えることができるようになります。
スポーツ観戦の場合は一人の選手に注目したり、ライブ映像の場合はあらゆる位置、角度からライブを視聴したり、これまでと違った視聴体験が可能になります。
VRが進化
VR、ARのリアルタイム映像をサーバーから視聴者へ配信するためには大容量のデータを送信する必要があり、その映像を360度自由に見まわしたり歩き回ったりするためには今度は視聴者側のアクションを瞬時にサーバー側に送信する必要があります。
そこで “超高速”、“低遅延”が売りの5Gの出番です。
超高速で高画質VR映像の大容量データを視聴者へ送信し、視聴者側からはアクションを低遅延でサーバー側に送信することによって高画質VR映像の配信が可能になります。
高画質なVR映像がリアルタイムで配信されるようになると、自宅に居ながらライブやスポーツ観戦をまるでその場にいるような感覚で楽しめるようになります。
現在は視聴者のアクションを映像に反映させる処理をHMD(ヘッドマウントディスプレイ)側で行っているため、Oculusシリーズに代表されるように大きめのHMDが必要ですが、この処理を全て5G回線を通じてサーバー側で行うことができるようになるとHMD側での処理が軽減し、HMDを小型化することができます。
一時のブームが終わり好きな人だけが利用している感のあるVRですが、映画の『レディ・プレイヤー1』のような小型HMDが登場し、VRに対するハードルが更に下がり、本格的な普及につながるかも知れません。
クラウドゲーム
GoogleのStadiaやSONYのPlaystation Now等、続々とクラウドゲームのサービスが登場しています。
現在の光回線による接続でも遊べますが、クラウドゲームは5Gが普及してからが本番です。
今後ゲームは4K、8Kの時代に突入し、高画質になればなるほどデータの容量は大きくなります。
5Gなら大容量のデータを超高速で送信できるので4K、8Kの大容量のゲームデータを遅延なく送信することができます。
また、ゲームではコントローラからのボタン入力を瞬時にコンピューター側に伝えてゲーム画面に反映させなければいけません。
特にアクションゲームにとって遅延は命取りなので、ここで5Gの低遅延が活きます。
現在PS4やSwitchのようなテレビゲームではこの処理を全てゲーム機内で行っていますが、5Gを介してサーバー側で行うことによってゲーム機自体も必要なくなります。
クラウドゲームが主流になるとGoogleのStadiaのようにコントローラーのみの販売が増えていくかも知れません。
自動運転
現在、自動運転の実現に向けて自動車が段階的に進化していますが、乗車して設定するだけで後は寝ていても目的地に到着するような『完全自動運転』の実現には全ての自動車をネット接続する必要があります。
ですが、自動車は常に動いているので光などの固定通信は使えませんし、無線LANも電波の届く範囲の問題で使えません。
そこで5Gの出番です。
高速大容量・低遅延・多数同時接続が可能な5Gを通じて全ての自動車をネット接続することで、道路を走る周囲の全ての自動車の状況をリアルタイムで把握することができ、安全性が飛躍的に高まり、完全自動運転が可能になります。
ただ、関係法律の整備の状況により、完全自動運転が確立されるのは5Gの次、6Gの時代になるのではないかとも言われています。
遠隔医療
テレビ電話を使った遠隔診察だけでなく、遠方から状況をリアルタイムで確認しながら手術の支援をしたり、医療現場での活用も期待されています。
遠方から状況を正確に確認するためには4K以上の高画質な動画を安定して送信し続ける必要があります。
救急車内等、有線でのネット接続が難しい状況でも5Gなら環境を構築でき、遠方からも適切な指示を送ることができます。
5Gのメリットである『低遅延』を活かし、遠方にいる医師が手術室のロボットを操作して手術を行う『遠隔手術』も技術的には可能になります。
身の回りのあらゆるものが常時ネット接続に
IOTと言う言葉が流行し、スマートウォッチに代表されるようなウェアラブル端末、スピーカー、冷蔵庫のような家電等、現在でも身の回りのものでネットに接続されるものはたくさんあります。
この流れは“多数同時接続”が可能な5Gが普及すると更に加速し、身の回りのありとあらゆるものが常時ネット接続されている状態になります。
例えばウェアラブル端末で心拍数や血圧等を計測し、データを家族や主治医と共有しておくと、身体に異変があればすぐに気付くことができ、病気の早期発見につながります。
お年寄りの独り暮らしの場合、身の回りの家電がネット接続され、データを遠方に住む家族と共有することで、いつもと生活パターンが違うことからすぐに異変に気付くこともできます。
これらは現在の技術でも可能ですが、多数同時接続が可能な5Gによって更に普及が加速していくと思われます。
その他、常時ネット接続しておくことで“モノ”の新たな利用価値が生まれるかも知れません。
5Gの問題点と課題

電波の届く距離が短い
5Gの電波は4Gまでと比較して遠くまで届きにくく、広い範囲に電波を届かせるためには多くの基地局を設置する必要があります。
2019年から一足先にサービスが開始されている韓国では、基地局の不足から5Gスマホを持った人々がポケモンGOのように5Gの電波を求めて歩き回ると言った光景が見られたようです。
多くの基地局を設置するためには、当然ですが多額の設備投資が必要になります。
人口が多く通信需要が大きい大都市圏には多額の設備投資が行われ、そうではない地方とでデジタル格差が生まれると言われています。
実際、5Gを全国網羅しようと思うと不採算エリアの方が多く、1企業がこれをやるのは難しいかも知れません。
携帯電話が普及し始めた頃、都市部ではどこでも当たり前のように電波が繋がりますが、人口の少ない地方では電波がつながるところを探すのに一苦労と言うことがありました。
5Gも開始からしばらくはこれと同じような状態になると思われます。
スマホでは5Gの恩恵がわかりにくい
1Gから2G、3Gの頃と違い、現在スマホを4Gで利用していても特に不満な点が見当たりません。
ウェブサイトの閲覧、SNSの利用、HD動画のストリーミング視聴に至るまで、スマホの画面の中で完結するようなサービスは4Gで充分快適に行えます。
5Gになったところで体感速度が上がるかと言うとそう変わらないと思われます。
大容量の動画データをダウンロードする場合等には速度の恩恵が受けられるかも知れませんが、ストリーミングで動画を見る場合や他のウェブサービスを利用する際、5G接続していてもスマホの画面に“5G”と表示されている以外、変化に気付かない可能性すらあります。
このことから、5Gのサービス開始当初はユーザーの間で5Gに対する失望感が広がってしまうかも知れません。
5Gならではの体験の開発が必要
上記のように、スマホを利用するだけなら5Gは必要ではないと言っても過言ではありません。
5Gならではの体験ができるガジェットやアプリ、サービスの開発が進めば5Gの必要性も高まりますが、しばらく時間がかかりそうです。
2001年に開始された3Gのサービスが2020年現在でもまだ続いている(auが2022年、docomoは26年に終了予定)ことを考えると、5Gのサービス開始後も4Gは継続して利用され、5Gと4Gの共存という時代が長く続きそうです。
5Gが大多数に普及しきる頃には6Gに対する期待が高まっているかも知れません。
まとめ
5Gってどう言うもので、何ができるのか、簡単にまとめてみました。
海外では5G対応のスマホが既にいくつか発売されていますが、日本でも春からのサービス開始に合わせて5G対応のスマホが登場します。
上にも書きましたが、サービスが開始されても5Gでなければ利用できないサービスと言うものがまだ存在しません。
開始当初は新しいもの好きの人だけがまず飛びつき、徐々に5G用の魅力的なアプリ、サービスが開発され、様子を見ながら一般ユーザーにも広がっていき、そのうち折りたたみスマホ等5G対応のスマホが当たり前になり否応なく全員5Gに移行ということになると思います。
将来的に5Gは私たちの生活に当たり前のように溶け込み、上に書いたような未来が実現されると思いますが、まずはスマホ用にスタートさせて基地局を増やし、どこまでのエリアをカバーできるかですね。
私は新しいもの好きですが、地方在住なのでまず間違いなく今年中に5Gが利用出来ることはありません。
残念ながらしばらく様子見になりますが、新しい時代が始まり、進化の過程が見られるのを楽しみにしています。







コメント